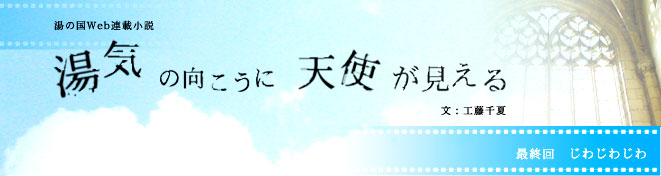 |
 結局、私は、そのまま三日無断欠勤した。電話をかける暇が一瞬もなかったというと嘘になるが、なんだかもう、すっかりイヤになってしまったのだ。大人気ないのはわかっていたが、そのままクビになっても構わなかった。ずっと病院に詰めていたから、電源も切っていたし。後から笹本クンに聞いたところによると、警察に行ったまま音信不通ということで、表だっては騒げないが、社内は秘かに騒然となっていたらしい。社会人失格である。でも、やっぱり、それどころじゃなかった。その昏睡から覚めることなく、おとーさんが逝ってしまったから。 結局、私は、そのまま三日無断欠勤した。電話をかける暇が一瞬もなかったというと嘘になるが、なんだかもう、すっかりイヤになってしまったのだ。大人気ないのはわかっていたが、そのままクビになっても構わなかった。ずっと病院に詰めていたから、電源も切っていたし。後から笹本クンに聞いたところによると、警察に行ったまま音信不通ということで、表だっては騒げないが、社内は秘かに騒然となっていたらしい。社会人失格である。でも、やっぱり、それどころじゃなかった。その昏睡から覚めることなく、おとーさんが逝ってしまったから。
一年七ヶ月も入院していたおとーさんを、一度は家に返してあげたい。珍しく、和ちゃんからの提案だ。長男の顔になっている。葬儀社のワゴンにおとーさんだけ乗せて、おかーさんと和ちゃんと私はタクシーで移動する。
「阿佐ヶ谷まで。運転手さん、とばしてください。あっちより、先に着きたいから」
座席に腰をおろすなり、和ちゃんは言った。
「そうね。おかえりって言わなきゃね」
おかーさんは、小さくそうつぶやくと、あとはなんにも言わなかった。 |
喪服を取りに部屋に戻ったとき、私は会社に、いや、笹本クンにやっと電話をした。
「連絡遅くなって、本当に申し訳ありませんでした」
「えーっとさ、キミさ、どういうつもりで……」
無断欠勤の謝罪、父親同然にお世話になっている人が亡くなったこと、葬儀が済んだら辞職願を持って会社に出向きたい旨、手短に告げた。
「いろいろご迷惑をおかけした上に、勝手ばかりで申し訳ありません」
「そう……北野さんが決めたことなら」
笹本クンは引き止めなかった。
「あの……映画フェスティバル、どうなりました?」
「ああ、アレは企画変更」
「変更って?」
「ごくフツーの、冠試写会になった。お風呂映画とかもう関係なく女性向けの新作やって、おみやげにバスタミンQ渡して」
「クライアント、よく下りませんでしたね」
「三枝さんの件はモミ消されて、先方の耳には結局入ってない。ま、お見事って感じ。彼女も担当代わったし」
たった三日。でも、世界の時間はちゃんと流れている。
「あの、稲田さんは?」
ちょっとだけ、間があいた。
「失踪」
「……」
「警察出てから行方不明。携帯も、事務所も自宅もつながらないし。北野さんとかけおちでもしたんじゃないかって思ってた」
「まさか……」
おっさん、失踪。おっさん、失踪。おっさん、失踪。なんだか、教会の鐘みたいにことばがガランガラン鳴ってる。意味が拡散していく。
「大丈夫なの? ……これからのこと、とか」
受話器の向こうの見えない笹本クンが、いつものように眼鏡をクッと上げるのが見えた。
「大丈夫、かな? たぶん」
ありがとう。それから、さよなら。私は、静かに電話を切った。 |
|
 そこからは、嫁同前というよりも、もう、私は嫁だった。気丈にふるまっていても、おかーさんは倒れる寸前だったし、ボストンに赴任中の弟の真ちゃんは、急いで帰国したもののただ右往左往してるだけだったし。和ちゃんと私は、まるで長年連れ添った夫婦みたいに物事を仕切った。だから、全部終わってみんなでお茶を飲んでいるとき、この家が自分の家じゃないって気づいて、実はちょっとびっくりしたのである。 そこからは、嫁同前というよりも、もう、私は嫁だった。気丈にふるまっていても、おかーさんは倒れる寸前だったし、ボストンに赴任中の弟の真ちゃんは、急いで帰国したもののただ右往左往してるだけだったし。和ちゃんと私は、まるで長年連れ添った夫婦みたいに物事を仕切った。だから、全部終わってみんなでお茶を飲んでいるとき、この家が自分の家じゃないって気づいて、実はちょっとびっくりしたのである。
「おつかれさま、って、つい言っちゃいますね。変ですけど」
「ほんと、絵美ちゃん、ありがとね。おつかれさまでした」
「やだ、そういう意味じゃなくて。おかーさんこそ」
「和ちゃんも真ちゃんも、おつかれさま」
黙っていた和ちゃんがぼそっと言う。
「死んだとーさんが、一番、おつかれさま」
「そうね、あと、藤の湯もおつかれさま」
えっ? おかーさん、それって、藤の湯、閉めるってことですか? |
|
「和ちゃんも真ちゃんも仕事あるしね、せっかく勤めてる会社辞めて欲しいなんて思わないし……。ボイラーの高見さんも、もう来年は七十だし、おとーさんいなくなったら、おかーさん、ひとりでがんばる元気なくなっちゃった」
和ちゃんを見た。なんにも言わない。
「ごめん。オレ帰って来れなくて」
弟の真ちゃんが先に謝った。和ちゃんは、やっぱりなんにも言わない。無口な男がかっこいいとでも思ってるの? 和ちゃんがなんにも言わなかったら、私がなにか言える訳ないじゃない。私がおかーさんを助けて、いっしょに藤の湯やります。だから、和ちゃんのお嫁さんにしてください。そんなこと、ひとりで盛り上がって言える訳ないじゃない。
「あの、おかーさん。私、会社、クビになっちゃったんです。だから、よかったら、私のこと、雇ってもらえませんか?」
「そんな、絵美ちゃんに甘える訳には……」
「だって、番台に上げてもらうって約束、まだだし」
和ちゃんが、口を開いた。
「おまえ、バカか」
やっとしゃべったら、これかい? カチンと来た。
「なによ、その言い方」
「自分ちの嫁に給料なんか払うか? 結婚するんだから、ちゃんと自覚持てよ」
「そんなのいつ決めたのよ」
「今」
「勝手に決めないでよ」
「おまえ、言ったろ。オレが本当にしたくなったら考えるって」
「……」
「言っとくけど、藤の湯のためでも、かーさんのためでもないから。おまえがここにいない生活はもう考えられない。だから、もう、帰るな」
ヒューッ。真ちゃんがガイジンみたいに口笛を吹いて、全部決まった。 |
|
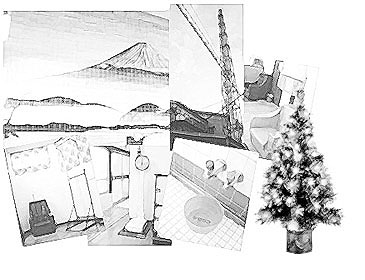 本格的に藤の湯の仕事をするようになって、三週間。三十六才という年齢は、私が思っていたよりも世間的にはずっとおばさんのようで、残念ながら、うら若き女性が番台にぃ……的な問題は何も起こらない。ホントは、頬くらい染めてあげた方が、かわいげがあっていいのかもしれない。 本格的に藤の湯の仕事をするようになって、三週間。三十六才という年齢は、私が思っていたよりも世間的にはずっとおばさんのようで、残念ながら、うら若き女性が番台にぃ……的な問題は何も起こらない。ホントは、頬くらい染めてあげた方が、かわいげがあっていいのかもしれない。
今どき、内風呂のない家なんてほとんどないだろう。でも、まだまだいろんな人たちが銭湯を訪れる。学生、水商売風の女性、板前さん、おじいちゃん、すぐに井戸端会議を開くおばちゃんたち、小学生の坊やを連れたお母さん……藤の湯版『こころの湯』が、毎日繰り広げられる。常連さんに喜んでもらいたくて、男湯、女湯、それぞれの脱衣場に家庭用のツリーなんか飾ってみた。イルミネーションは、毎年そこに飾られているかのように、静かに点滅を続ける。おっさん、どうしてるんだろ? あのポメの目で、また、どっかの女の子に魔法をかけたりしてるんだろうか? 「この娘に、もっと幸せがおりてきますように」って。そのうち、湯船からオーソレミーオが聴こえてきたりして……あれっ、聴こえるよ、男湯から、歌詞が全部オーソレミーオの下手っくそな唄が。♪オーソレミーオ、オーソレミォー、オーソレミーオ、オーソレミォー……唄声はどんどんどんどん大きくなって、男湯の天井にも女湯の天井にも反響して、天国に響く賛美歌みたいなパイプオルガン付きの混声合唱なって、脱衣場ごと、藤の湯ごとまるごと包み込んで、そして、ふっと消えた。次の瞬間、背広姿の和ちゃんが男湯ののれんをくぐる。
「ただいま、鍋の材料買ってきたから」
「……うん」
「どしたの?」
「……なんでもない」
「いいだろ、別にイブにフレンチとか食わなくたって」
「そんなこと言ってないでしょ」
「トナカイの肉、奮発したから」
和ちゃんの顔を見ながら、自分の分岐点をしみじみ思う。ああ、おっさんって、本当にいたんだろうか?
「スマイル、スマイル」
えっ? 和ちゃんは、チカチカきれいなクリスマス・ツリーの脇を通って、歌なんか歌いながら母屋に向かう。♪だいじょうぶ、マイフレンド〜。そうだね、大丈夫、うん。大丈夫。 |
|
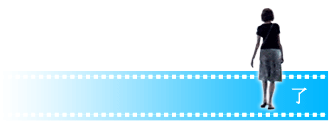 |